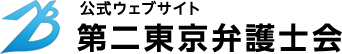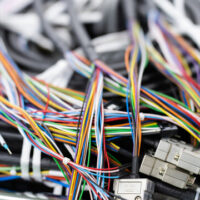交通事故発生後にまずすべきこと ~初期対応の流れ~

交通事故を起こしてしまった、または、交通事故に遭ってしまった・・・・
そのような状況だと人はパニックになり、どのような行動をとって良いかわからなくなります。
今回は、交通事故に備えたい方や交通事故直後の初動を知りたい方向けに、事故直後にすべきことを解説します。
1 負傷者の救護(救助・応急措置)
事故でケガをした人がいれば、まず応急処置を行うか、安全が確保できる範囲で動かさず救急車を要請します。
道路交通法上、運転者には「救護義務」が課されています(負傷者がいる事故では救護措置を怠ると罰則あります。道路交通法72条。)
頭部・頸部に損傷の可能性がある場合は、むやみに動かさず、救急隊の指示を仰ぐべきです。
2 事故現場の安全確保
まず、二次的な事故を防ぐため、後続車への注意喚起のため、発煙筒や三角停止板を設置しましょう。
発煙筒は助手席足元にあることが多いです(トンネル内での使用はNG)。
また、三角停止板は高速道路では使用義務があります。後方50メートルに設置しましょう。
3 警察への通報・届出
事故が起こったら、たとえ軽微な事故でも警察へ通報しましょう(110番、または最寄りの交番・警察署に連絡)。道路交通法72条では警察への報告義務があります。
通報しないと「報告義務違反」として罰則を科される可能性もありますのでご注意ください(3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金)。
また、通報をしないと「交通事故証明書」が発行されず、保険会社への保険金請求や示談交渉の際に不利になることがあります。
よくあるのが、被害者から「けがはないので大丈夫です」と言われたため、警察に通報しなかったパターンです。
たとえこのような場合でも報告義務違反となります(これを理由に逮捕・勾留された事案もあります。)。
なお、ドライブレコーダーを搭載している場合、その映像も警察に提出でき、過失割合の判断材料になることがあります。
4 相手方との情報交換
警察が到着するまでの間に、相手側ドライバーに、氏名・住所・連絡先・運転免許証番号・保険会社名・契約番号などを確認します。
相手方が嘘の情報を伝えてくる可能性があるため、相手の免許証や保険証の写真を撮らせてもらったりする方法も有効です。
また、事故車両が他人名義(借り物・レンタカー等)の場合は、所有者情報も把握しておくとよいでしょう。
なお、この時点で相手方とは絶対に示談をしないでください!
あとで症状や損害が拡大したとしても、支払いがされない可能性が高くなります。
5 警察捜査への協力
人身事故の場合、警察が事故状況について実況見分を行います。そこでは当事者から事故時の状況を聞き取り、現場を検証します。
なお、提出された実況見分調書は、過失割合等を判断する重要な証拠となります。
また、初期段階で物損事故扱いとなっても、後から人身事故へ切り替え可能なケースがあります。人身事故扱いにしておかないと、後日の示談交渉や保険金請求で不利になる可能性があるため積極的に人身事故への切り替えをしましょう。
6 保険会社への連絡
自分が加入している保険会社には、できるだけ早く事故発生の旨を連絡しておきましょう。保険契約には「事故発生を速やかに通知する義務」があることが多いです。
また、保険契約に「弁護士費用特約」が付いていれば(多くの任意自動車保険でオプションとして設定可能)、弁護士への相談料・着手金・報酬金を保険会社が肩代わりしてくれるケースがあります。
弁護士費用特約は、自動車保険だけでなく、居住する住まいの火災保険やその他傷害保険等にも付されている可能性があるため、事故後、積極的に自身が契約している保険契約を確認しましょう。
7 医療機関での受診(ケガの有無にかかわらず)
できれば事故日に病院での受診をしてください。
その後の通院は弁護士に相談のうえで、行うことをお勧めいたします。
たとえば、病院ではなく整骨院・接骨院などでの治療を受ける場合、医師の関与(同意や紹介)なしで通っていると、保険会社が治療費支払いを認めないこともあるからです。
また、ケガをしていないように見えても、事故の衝撃で内部的な損傷や後遺障害のリスクがあります。事故当時は興奮状態やショックで痛みに気づかないケースもあるため、必ず受診するようにしましょう。
初診・通院記録を残すことで、事故と損害(後遺障害)との因果関係を立証しやすくなります。
通院を継続する際は、医師の指示に従い、規則的に受診し、記録(診療明細や通院にかかった交通費の領収証など)を保管しておきましょう。
もうケガが治ったと思い、自己判断で通院を中断すると、慰謝料や治療費請求が減額されるリスクがあるので、通院を中断する際は必ず弁護士に相談しましょう。
8 弁護士に相談・依頼するメリット
交通事故の慰謝料請求や保険金請求を個人で行うことは可能ですが、状況によっては非常に高度な専門知識や交渉力が求められます。以下では「弁護士に相談すべきタイミング」、「依頼のメリット」、「弁護士費用特約の活用」について整理します。
⑴ 弁護士に相談すべきタイミング
事故直後が望ましいです。理由としては、具体的な通院方針を決めることができ、結果として保険金額、慰謝料金額の増額につながる可能性が高くなります。
また、保険会社との交渉がうまくいかないときも有効です。
途中から弁護士が介入する場合であっても、獲得金額が増額することがあります。
いずれにせよ、早期に弁護士が介入すれば通院方針や金額の見立てをあらかじめ把握することが可能となるため、不利益を未然に防ぎやすくなります。
⑵ 弁護士に依頼するメリット
① 損害額・慰謝料の検討支援
相場や判例に照らして妥当な損害額を把握し、保険会社の提示額をチェックします。
② 交渉代行・主導権を握る
保険会社との交渉を弁護士が代行することで、自分自身で対応する手間を回避できます。
③ 後遺障害等級申請・異議申立支援
等級認定や異議申立ての手続には専門的ノウハウが求められるため、経験ある弁護士のサポートが有効です。
④ 精神的負担の軽減
保険会社との連絡・主張整理・書面作成などを任せられるため、事故後の対応に追われるストレスを軽減できます。
⑶ 弁護士費用特約・費用負担の軽減
多くの自動車保険には「弁護士費用特約」がオプションでつけられており、相談料・着手金・報酬金などを特約で補填できる場合があります。
この特約を使っても、保険の等級が下がることは通常ありません。
弁護士費用特約には上限金額が定められているため(例えば300万円程度)、上限金額や対象範囲(弁護士に依頼できる内容)を保険契約書で確認しておくことが重要です。
9 まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回はどうしてもうまくいかない交通事故直後の初動対応について解説しました。
もし弁護士費用特約があるならば、早期に弁護士に相談することをお勧めいたします。
あかがね法律事務所では、交通事故案件も多く取り扱っております。
下記よりご相談をお待ちしております。