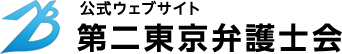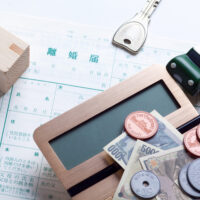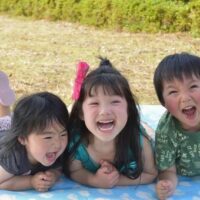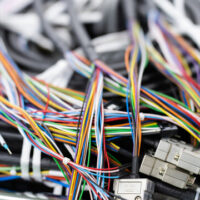令和8年(2026年)導入予定の共同親権とは?〜離婚後も親権を共有できる制度へ

令和5年5月17日、離婚後の親権制度を見直す「民法等の一部を改正する法律」が国会で成立し、公布されました。
この改正によって、父母が離婚後も共同で親権を持つ「共同親権(選択的共同親権)」制度が、令和8年(2026年)までに施行される見込みです。
改正法案では、子の養育・面会交流・親権・監護のルールを明確化し、子どもの利益を重視する枠組みの整備が目指されています。
今回はこの共同親権について解説をします。
1 共同親権の主な変更点とポイント
⑴ 離婚時の親権の選択肢が拡大
これまでは、離婚後は父母のうち一方が親権者となる「単独親権」が原則とされてきました。
改正後は、協議離婚時には父母で共同親権とするか、単独親権とするかを選べるようになります。
また、裁判離婚・調停離婚の場合も、共同親権か単独親権かを家庭裁判所は判断することが可能となります。
⑵ 既に離婚しているケースへの影響
既に離婚した夫婦についても、改正後は共同親権への変更申立てによって、現行の単独親権から共同親権へ移行することも可能になります。
ただし、共同親権への移行は無条件に認められるわけではなく、家庭裁判所が個別の事情を踏まえて判断するため、実際に申立てが認められる可能性については未知数です。
⑶ 共同親権が行使されるとどうなる?
共同親権が認められると、子どもの居住地、進学、重要な医療措置など重要事項について父母双方で協議・合意をする必要があります。
ただし一部の事項については例外的に単独で決めることができます。
これは後述で紹介します。
⑷ 共同親権の例外は?単独で決めるには。
まず、①子どもへのDV・虐待のおそれがある場合、または、②父母間でDV虐待のおそれがあり共同親権行使が困難である場合には、裁判所は単独親権の判断をしなければいけません。
また、共同親権であったとしても、「急迫の事情」や「日常の行為」は単独で行うことができます。
「急迫の事情」は、虐待からの避難、緊急治療行為、入学手続き等の緊急性が高いものを指します。
「日常の行為」は、普段の食事の献立(夕飯を何にするか)等の夫婦間で協議、合意をする必要性が乏しいものを指します。
2 共同親権のメリットと懸念点
⑴ メリット
- 親権争いを回避・緩和しやすくなる
- 子どもが両親との関係を継続しやすくなる
- 子育てに関し、意思決定の公平性・透明性が向上する
- 親子間の信頼・関与関係の維持という観点でプラスになる
⑵ 懸念点・リスク
- 親の間で方針が対立する場面が増え、調整コストが上がる
- 両親がDV・モラハラ関係にある場合、身体の安全や子どもの心理的負荷が懸念される
- 両親が地理的に離れている場合、協議・合意が困難
このように、共同親権は一律に良いことばかりではなく、デメリットやリスクもあります。
したがって、まずは子どもの利益を中心に考え、共同親権にすべきか検討しましょう。
3 まとめ
共同親権は、これまでの「離婚後は単独親権が原則」という枠組みを大きく変える制度です。
離婚後も父母がともに子どもの将来に関わることができる一方で、親同士の意見対立やトラブルが増える可能性もあります。
特に、
- 離婚を検討しているが、親権をどうするか迷っている
- 共同親権になったときの生活・面会・養育費の影響を知りたい
- DVやモラハラなど安全面の不安がある
といった方は、法改正後の運用を見据えて早めに弁護士へ相談しておくことが重要です。
弁護士に相談すれば、親権・面会交流・養育費などを総合的に整理したうえで、「単独親権が適切か」「共同親権を選ぶべきか」といった判断を法律的にサポートできます。
共同親権制度開始に備え、いまから正確な知識と準備を進めましょう。
お子さまの幸せと安全を第一に考えるためにも、まずは弁護士へご相談ください。
あかがね法律事務所では、離婚事案も多数取り扱っています。
以下よりお気軽にご相談ください。