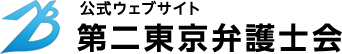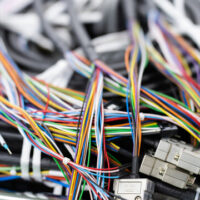早期釈放に向けた活動について(被告人編)

起訴されると、これまで「被疑者」と呼ばれていた人は「被告人」に呼び方が変わります。
被告人段階であっても早期釈放は可能なのでしょうか?
今回は、被告人段階の早期釈放、とくに「保釈」に解説します。
1 保釈とは何か?
まず、保釈制度の基本的な意味と役割を押さえておきましょう。
「保釈(ほしゃく)」とは、起訴後の被告人に対し、一定の条件(主に保釈保証金の納付や居住制限など)を付すことで、被告人の身体拘束(勾留)を一時的に解く制度です。
ここで一般的に誤解されているのは、保釈は、被疑者段階(逮捕から起訴に至るまで)では認められず、あくまで起訴後の被告人段階で適用される制度です。
※なお、被疑者段階での早期釈放手続きは「準抗告」といいます。
保釈制度の根底には、「逃亡や証拠隠滅のおそれがなければ、身体拘束を長く続けるのは被告人の防御権を著しく制約しうる」という考え方があります。
もちろん、保釈された後でも、裁判手続きは通常どおり続行されます。保釈はあくまで「身体拘束からの解放」であり、有罪か無罪かを決めるものではありません。
2 保釈は誰が請求できる?
保釈を請求できるのは、次の者です。
- 被告人本人
- 弁護人
- 法定代理人
- 配偶者
- 直系親族または兄弟姉妹
また、保釈請求は、起訴後(公判請求後)であればいつでも請求できます。
3 保釈の種類と認められるための要件
保釈を認めるかどうかは裁判所が判断します。大きく分けて2種類の保釈が存在します。
- 権利保釈:被告人が法定の除外事由に該当しない場合、保釈を請求すれば裁判所はこれを許可しなければならないという性質のもの。
法定の除外事由は刑事訴訟法89条で定められています。
| 第89条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。 一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。 二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。 三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。 四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏い怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。 六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。 |
- 裁量保釈:被告人が法定の除外事由にあたる可能性がある場合でも、裁判所が刑事訴訟法90条に記載された逃亡・罪証隠滅などの可能性を慎重に判断し、「保釈を許すのが相当」と認めた場合に許可されるもの。
| 第90条 裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。 |
4 保釈請求の流れ
保釈を請求してから、身柄が解放されるまで一般的には次の手順で進みます。
① 保釈請求書の提出
被告人本人、弁護人、親族等が保釈請求書を作成し、裁判所に提出します。身元引受書などを添付することがあります。
② 検察官意見の聴取
裁判所は検察官から意見聴取(逃亡・証拠隠滅などのリスクについての見解)を求めます。
③ 裁判所の審理・判断
双方の意見、主張を踏まえ、裁判所が保釈の可否を判断します。権利保釈を認めない事由が存在しなかったり、裁量保釈を認めるのが相当であると判断された場合には、保釈許可決定が出されます。
④ 保釈保証金の納付
保釈が認められた場合、裁判所が定めた保釈保証金(保釈金)を納付します。納付後にはじめて被告人の身体拘束が解かれます。
⑤ 裁判終了後の保釈保証金の返還
裁判が終了した場合、被告人が逃亡や保釈の条件違反をしていなければ、原則として保釈金は全額返還されます。
5 保釈保証金の相場
保釈保証金の額は、事件の種類、被告人の資力、逃亡リスク、証拠関係などを総合判断して決められます。
一般的な相場として、100万円〜300万円程度であることが多いです。
これに対して、重大犯罪や複数前科がある場合、芸能人等の事件である場合には、金額が大きくなることがあります。
6 よくある質問
Q1:保釈を請求すれば必ず認められる?
→ いいえ。保釈請求が認められるには、逃亡や証拠隠滅の可能性が十分に低いと判断されることが必要です。重大犯罪、被告人の住居等が定まっていない場合などでは、保釈が認められないことがあります。
Q2:保釈保証金は戻ってくるの?
→ はい、裁判終了後、被告人が出廷義務や保釈条件を守っていれば、原則として全額返還されます。ただし、逃亡や保釈条件を破ったりした場合には、没収をされることがありますので注意しましょう。
Q3:保釈中に外泊や転居はできる?
→ 原則として保釈条件の一つとして住居制限がされます。外泊や転居が認められるかどうかは裁判所の許可次第です。無断で転居等をすると保釈保証金没収のリスクがあります。
7 まとめ
保釈は、起訴後でも身柄を解放できる有効な手段です。
しかし、保釈請求は誰でも簡単に通るものではなく、
「逃亡や証拠隠滅の恐れがないこと」を丁寧に主張する必要があります。
そのためには、
- 保釈保証金の準備や家族の協力体制の整備
- 保釈請求書の作成
- 裁判所・検察官とのやり取り
など、専門的な判断と迅速な対応が欠かせません。
刑事事件の保釈は、弁護士の経験と戦略によって結果が大きく変わる場面です。
ご家族が勾留されたままの状況を一日でも早く解消したい場合は、弁護士に相談し、すぐに保釈請求の準備を始めましょう。
早期の弁護士への依頼が、保釈成功への最短ルートです。
あかがね法律事務所は刑事事件も豊富に取り扱っておりますので、お気軽にお問い合せください。