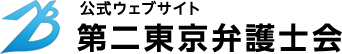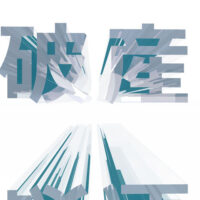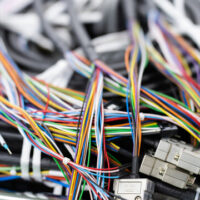東京地裁での自己破産手続きの流れ|申立から免責までのステップと注意点

東京地方裁判所(東京地裁)の倒産部(民事第20部)が、東京エリアにおける破産・再生などの倒産事件を扱います。
東京地裁では、「即日面接(破産申立の初期段階で裁判官と面接を行う制度)」や、「少額管財手続」の活用などの運用が積極的に行われており、手続きの迅速化に注力しています。
ただし、すべての破産申立てが同じ流れをたどるわけではなく、債務者の財産・借入状況や免責不許可事由の有無等により、「同時廃止事件」になるか「管財事件」になるかで手順や期間が異なります。
以下では、東京地裁での破産手続きについて、その流れを、ステップごとに解説します。
1 破産手続きの概要(申立てから免責決定まで)
自己破産の主な流れは、おおむね次のとおりとなります。
① 弁護士への相談・受任 → 債権調査・書類準備
② 破産申立て
③ 即日面接(申立て直後に裁判官との面接)
④ 裁判所による手続き方式の判断(同時廃止事件か管財事件へ振り分け)⑤ 破産手続開始決定
⑥ 管財事件ならば管財人との面談・調査
⑦ 債権者集会・免責審尋(免責許可の可否判断のための手続き)
⑧ 免責許可決定
⑨ 手続終結
以降、この流れをステージごとに詳しく見ていきます。
2 弁護士への相談・受任・債権調査
まずは、弁護士等に相談の上で、破産手続きを依頼します。借金の総額、資産の有無、収支状況、過去の浪費・ギャンブルの有無などを整理し、どのような手続き(破産・個人再生・任意整理等)が最適か判断します。
弁護士に依頼すると、弁護士から各債権者に対し「受任通知」が送付されます。この受任通知は、弁護士の介入を知らせるとともに債権者ごとに取引履歴開示請求を行います。
この受任通知送付により、債権者から依頼者への支払い請求や督促はいったんストップします。そして、債権者から弁護士宛に債権調査票(借入履歴や借入残高を記載した書面)が送付され、依頼者の借り入れ状況が明確になります。
この段階で依頼者から弁護士に対する債権者の申告漏れがあると、その後の手続きで遅れやトラブルが発生しやすいです。相談の段階でできる限り丁寧に債権者の数や具体的な借入金額を申告しましょう。
弁護士に依頼するメリットについてはこちらの記事で解説をしています。
3 破産申立て
裁判所への提出書類等の準備が整ったら、あなたの居住地を管轄する裁判所に破産手続開始および免責許可の申立書を提出します。
申立て時には、必要書類を添付し、印紙や郵券(郵便切手)や予納金等を納付する必要があります。
書類は意外と数が多いのでこちらの記事を読んでおさらいしておきましょう。
4 即日面接
東京地裁では、申立て後、3開庁日以内(休日を含まない日で3日以内)に「即日面接」が行われる運用があります。
即日面接を希望する場合には、その旨を申立書で選択欄にチェックを入れておく必要があります。
即日面接では、裁判官と申立代理人(通常は弁護士)との面接が行われます。この面接で、借り入れや破産の原因・経緯、収入・資産状況、免責不許可事由等が裁判官から口頭で確認されます。
この時点で、破産手続きが「同時廃止事件に相当するか」「管財事件に振り分けるか」が判断されます。
なお、東京地裁では、管財事件であったとしても多くの事件が「少額管財事件」という形式で扱われる運用があり、通常の管財手続よりも管財費用が安い形で処理されることが多いです。
即日面接が終了すると、裁判所は破産管財人候補者の選定を行い、手続きを進めます。
5 同時廃止事件か管財事件か
即日面接の結果、申立てが認められ、かつ「債務者に財産がほとんどない」「免責不許可事由がない」と判断されれば、「同時廃止事件」として処理されます。
この場合、破産手続開始と同時に破産手続が終了し、免責手続へと進みます。
他方で、「債務者に一定の資産がある」、「事情が複雑で調査が必要」な場合には「管財事件」に振り分けられます。
管財事件では、破産管財人が選任され、債務者の資産を換価・調査し、債権者に配当を行うなど、より手続が複雑になります。さらに原則として管財費用を最低でも20万円納める必要があるため、債務者にとっては大きな出費となります。
6 管財人面談・調査
管財事件に振り分けられた場合、破産管財人が選任され、債務者と破産管財人との打合せ(面談)が行われます。打合せでは、申立書記載内容の裏付け、資産の引継ぎ、手続の進め方、換価見込み・売却予定財産、債権者配当案などが話し合われます。
なお、この時点で管財人は債務者の財産を保全しておく必要があるため、債務者は通帳を記帳の上で、管財人面談で通帳原本およびキャッシュカード等を破産管財人に預けることになります。
その後、管財人は、財産調査を進め、債権者への配当可能性を評価し、換価・売却手続を進めます。
7 債権者集会・免責審尋
破産申立てから約3か月後に管財人の調査結果に基づき、債権者集会および免責審尋(めんせきしんじん)が同時に実施されます。
ここで、管財人は債権者や裁判所に対し調査結果の報告・説明を行います。
他方で、債務者は免責許可の可否を判断するための審尋(裁判官からの直接聴取)が行われます。
ここでは債務者本人が裁判所に出廷して、借金の経過・原因、財産・収支状況、反省や将来の見通しなどを口頭で説明することが求められます。
そして免責不許可事由がないか、裁量免責判断で問題ないか等が重点的に審査されます。
免責不許可事由についてはこちらの記事をご覧ください。
8 免責許可決定
免責許可が裁判所から認められれば、免責許可決定がなされます。この決定が確定すれば、債務者は破産者の地位から離れ、借金返済義務は免除されます(ただし非免責債権を除きます。)。
免責許可決定が確定すれば破産手続きは終結します。
非免責債権についてはこちらで解説しています。
9 まとめ
いかがでしたでしょうか。
東京地裁で自己破産を申し立てる場合、破産手続きの流れを理解しておくことは非常に重要です。特に、即日面接・同時廃止/管財判断・管財人面談・免責審尋といった段階では、東京地裁特有の運用がなされています。
手続きをスムーズに進めるには、弁護士を代理人とし、書類準備を正確に行うことが不可欠です。
また、裁判所や管財人とのやり取り、追加資料提出、説明義務など、臨機応変な対応力も必要になります。
破産を検討されている方は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
あかがね法律事務所では破産事件も多く取り扱っています。
以下よりご相談お待ちしております。