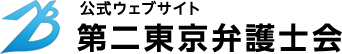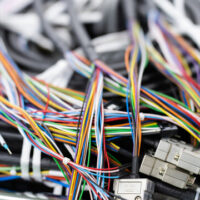発信者情報開示請求に必要な「権利侵害のパターン」とは?

投稿者を特定する手続、「発信者情報開示請求」の流れについては前回ご説明したとおりです。まだの方は、以下の記事をご覧ください。
インターネット上で誹謗中傷を受けたとき、多くの方が「書き込んだ人物を特定したい」と考えます。
しかし、どんな投稿でも必ず発信者情報開示請求が認められるわけではありません。
プロバイダ責任制限法に基づき発信者情報を開示してもらうためには、裁判所に対して「人格権侵害」があったことを具体的に主張・立証する必要があります。
今回は、その中でも代表的な3つの権利侵害(名誉権・名誉感情・プライバシー権)について解説します。
1 名誉権の侵害
名誉権とは?
法律上の「名誉」とは、人に対する社会的評価を指します。つまり、「人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価」をいいます(最大判昭和61年6月11日)。
この権利は個人だけでなく、企業や法人にも認められるものです。
投稿のタイプ
名誉権侵害には大きく分けて以下の2種類があります。
- 事実摘示型:事実かどうかを証拠で判断できるもの
例:「A君はBさんの机の中にごみをいれた。」という投稿の場合、Bさんの供述や被害状況の写真などの証拠から、当該投稿の真偽を判断できる - 意見論評型:証拠で真偽を判定できないもの
例:「Aは無能だ」「Aは性格が悪い」
特に事実摘示型の投稿は、開示請求が認められやすい傾向にあります。
他方で意見論評型の投稿は証拠によってその真偽を判定できないことが多いため、開示請求が困難になる傾向があります。
2 名誉感情の侵害
名誉感情とは?
「人が自己自身の人格的価値について有する主観的な評価」を指します。簡単に表現するのであれば、自身の誇りやプライドのようなものです。
これは自然人(人)にしか認められず、企業や法人などには適用されません。
判断基準
名誉感情は、先ほど説明した名誉権よりも弱い権利であり、発信者情報開示請求が認められるためには、一定のレベル以上の侮辱的行為や発言が必要となります。
この一定のレベル以上かどうかの判断基準について、最高裁判所は、「社会通念上許される限度を超える侮辱的行為」と判断しています(最三小判平成22年4月13日)。
これだけだとまだよくわからないですよね?
さらに下級審では、「誰であっても名誉感情を侵害されることになるような、看過しがたい、明確かつ程度の著しい侵害」というように、より具体化した裁判例も多くあらわれてきています(さいたま地判平29年7月19日)。
例えば、
- 一度だけ「Aはブス」と書かれた → 原則として侵害に当たらない
- 「Aはブス」という投稿が毎日50件、100日間続いた → 社会的に許されないレベルとされ、名誉感情侵害に当たる可能性が高い
つまり、発言の内容・量・継続期間が重要な判断材料となります。
3 プライバシー権の侵害
プライバシー権とは?
「自分に関する情報をみだりに公表されない権利」です。これは個人にのみ認められる権利です。
成立要件
判例は、以下の3つの要件を満たすとプライバシー権侵害に該当すると判断しています。
① 私生活上の事実またはそれらしく受け取られるおそれのある事柄
② 一般人の感覚を基準として、書き込まれた人の立場に立った場合、公開をしてほしくないと考えられる事柄
③ 一般的に知られてはいない事実であること
例:「AはB子と不倫している」という投稿。このような不倫、浮気、男女問題等に関する書込みは、プライバシー権侵害になり得ます。
4 まとめ
発信者情報開示請求では、単に「誹謗中傷された」と訴えるだけでは不十分です。
- 名誉権侵害:社会的評価を下げる投稿
- 名誉感情侵害:度を超えた侮辱的な投稿
- プライバシー権侵害:不倫など私生活の秘密を暴露する投稿
これらを区別し、正確に主張することが、開示請求を認めてもらうための第一歩です。
しかしながら以下の観点から自身だけで対応をするのは難しいと考えられています。
- どの権利侵害に当たるのかの判断が難しい
- 裁判所に通用する主張・証拠を整える必要がある
- ログ保存期間を考慮し、請求するための迅速な対応が必要
こうした理由から、被害にあわれた方は一人で悩まず、弁護士に相談することを強くおすすめします。
あかがね法律事務所では、これまで数多くのネットトラブルを扱ってきた実績があり、依頼者に最適な解決策をご提案しています。
下記よりご相談をお待ちしております。