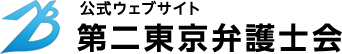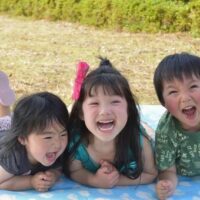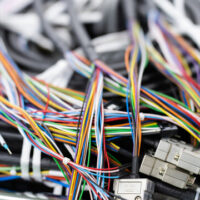財産分与とは何か? 【弁護士が解説する基本の整理】

「離婚の際は財産分与をする」
皆さん、「財産分与」という言葉は知っているかもしれませんが、その内容やルールについてはあまり広くは知られていません。
今回は、財産分与のルールやどのような財産が分与対象になるかを解説します。
1 財産分与の法的根拠と意義
財産分与は、離婚時に夫婦の一方が他方に対して財産を分け与える請求をできる制度であり、民法第768条および第771条に規定されています。
| (財産分与) 第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。 3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。 (協議上の離婚の規定の準用) 第771条 第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。 |
これは、婚姻中に夫婦が協力して築き上げた財産を清算し、離婚後の新たなスタートを公平にするという性格を持つものです。
単なる「慰謝料」ではなく、財産を分けあう手続きであり、別に慰謝料の請求権を主張することも可能です。
2 財産分与の3つの性質
財産分与には、実務上、以下の3つの性質に区別されることがあります。この中で、特に「清算的財産分与」が最も争点になりやすいです。
| 種類 | 内容 | 補足例 |
|---|---|---|
| 清算的財産分与 | 婚姻中の共同財産を離婚時に清算・分配するもの | 通常のケースで一番多い形式 |
| 扶養的財産分与 | 離婚後、収入能力に差がある一方を扶養する意味での分与 | 例:専業主婦だった配偶者の生活保障の趣旨等 |
| 慰謝料的財産分与 | 離婚原因を作った側に課す損害賠償的な意味を持つ分与 | 財産分与の割合や対象を調整して請求されるケースもあるが多くは財産分与とは別の「慰謝料」という項目で請求される |
3 財産分与の対象になる財産
⑴ 対象となる財産(共有財産)
財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦の協力関係の中で形成・取得された財産です。これを「共有財産」といいます。
具体的には次のようなものが挙げられます。
- 預貯金、現金
- 有価証券(株式・債券など)
- 不動産(土地・建物)
- 自動車・バイク
- 保険の解約返戻金
- 企業年金等
- その他高額動産・ゴルフ会員権などの資産性のある物
⑵ 対象外となる可能性が高い財産(特有財産)
一方で、「婚姻前から一方が所有していた財産」や「婚姻中に夫婦の協力とは無関係に取得した財産」は財産分与の対象外となります。これを「特有財産」といいます。(民法第762条1項)。
| (夫婦間における財産の帰属) 第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 |
以下のような財産は通常、分与対象から除かれることが多いと考えられています。
- 婚姻前に取得した財産(結婚前から持っていた預金・不動産など)
- 相続や贈与により個別に取得した財産(婚姻中であっても、他方の貢献が薄いと判断されるもの)
- 別居後に取得した財産
4 財産分与の割合とルール
⑴ 原則:2分の1ルール
離婚時には、特段の事情がない限り、共有財産を夫婦で2分の1ずつ分けるのが原則です。
⑵ 修正・例外が認められるケース
ただし、以下のような事情があると、分与割合が2分の1から変動することがあります。
- 財産維持・管理の貢献度に顕著な差がある
- 婚姻期間が極端に短い、または一方が離婚前から財産を独自に取得していたなどの事情
- 一方が著しい浪費または債務負担をしたために他方の財産が減少した場合
- 特別な貢献(例:家業への協力、事業拡大のための支援等)を立証できる場合
- 医師や弁護士等、夫婦共有財産が個人の能力によって築かれた場合
5 あると便利。財産分与で押さえるべき資料
離婚に当たっては、まず、財産分与の対象を判断するための資料をできる限り揃えましょう。
例えば次のようなものです。
- 預貯金通帳、取引明細、証券取引記録
- 不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書
- 車検証
- 保険証券・解約返戻金資料
- 退職金見込み額・年金記録
- 借入金・ローン契約書・返済明細
- クレジットカード明細・領収書
6 よくある質問と注意点
Q1:財産分与は必ず請求できる?
→ 原則として離婚後2年以内に請求しなければ時効によって請求できなくなる点に注意が必要です。
Q2:名義が自分名義でも全部取られてしまうの?
→ 名義が単独であっても、婚姻中の協力があれば実質共有財産と認められることがあります。
Q3:ローン返済中の不動産はどうなる?
→ 不動産の評価額(売却金額)からローン残額や売却諸費用等を差し引いた残額が財産分与の対象となります。
Q4:慰謝料と財産分与を混同していい?
→ 慰謝料は精神的損害を金銭評価する請求であり、原則として別途主張するものです。ただし、合意の中で財産分与の割合を調整して慰謝料的な意味合いを含めるケースはあります。
Q5:財産分与はいつの時点の財産を対象といするの?
→ 財産分与の対象、すなわち共有財産であるかの基準は原則として「別居時」になります。
Q6:弁護士に頼むメリットは?
→ 財産把握の資料把握・証拠整理・主張立証、相手との交渉代理、調停・訴訟対応、強制執行可能な文書作成など、法律的観点から有益なアドバイスを行うことができます。
7 まとめ
財産分与は、単なる「財産の半分を分ける」手続きではなく、婚姻中に築いた財産をどのように公平に分けるかを決める、とても重要なものです。預貯金や不動産だけでなく、退職金や保険、株式など多岐にわたるため、正しく把握して適切に主張しなければ、本来受け取れるはずの財産を失ってしまう可能性もあります。
しかし、財産の範囲や評価方法をめぐっては、相手方との意見が食い違いやすく、感情的な対立にも発展しがちです。こうした場面では、法律の専門知識と交渉力を持つ弁護士に依頼することで、公平かつ確実な財産分与を実現できる可能性が高まります。
「どの財産が対象になるのか分からない」「相手が財産を隠しているようで不安」と感じている方は、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
あかがね法律事務所では、離婚事案も多数取り扱っています。
以下よりお気軽にご相談ください。