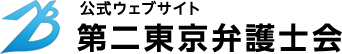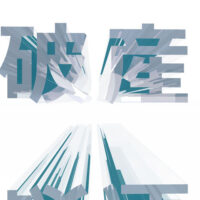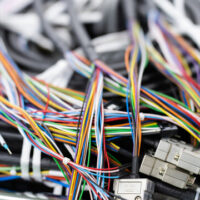非免責債権とは? ― 自己破産しても消えない義務

自己破産手続を経て「免責許可」が確定すると、通常、破産債権(借金など)について支払い義務を免れることができます。
しかし、破産法には「免責の効果が及ばない債権」が定められており、これを非免責債権(ひめんせきさいけん)といいます。
つまり、たとえ免責許可が下りたとしても、非免責債権に該当するものは、支払い義務が残ってしまうのです。
今回は非免責債権について解説をしていきます。
1 非免責債権とは
非免責債権は破産法第253条1項に列挙されています。
非免責債権は破産債権の一部ではあるものの、免責決定が出た場合であっても、その免責の効果が及びません。
要するに、免責決定が出たとしても残り続ける債権を言います。
| (免責許可の決定の効力等) 第253条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。 一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。) 二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。) 四 次に掲げる義務に係る請求権 イ 民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務 ロ 民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務 ハ 民法第766条(同法第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務 ニ 民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務 ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの 五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権 六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。) 七 罰金等の請求権 |
以下では、代表的な非免責債権について紹介します。
2 非免責債権の種類と性質
① 租税等の請求権(一号)
最も典型的なものが「租税等の請求権」です。つまり、所得税、住民税、固定資産税、自動車税、相続税、贈与税などの税金や、保険料・公的年金・国民健康保険料などの公的負担金は免責決定によっても残り続けます。
したがって、住民税や固定資産税、国民年金、国民健康保険料などを滞納していた場合には、たとえ破産手続きを経ても支払い義務は消えません。
ただし、公共料金(電気・ガス・上水道など)については、原則免責となります。下水料金のみがこの租税等と同様の性質を有するため非免責債権となります。
なお、ライフラインについては、破産手続きが開始したとしても「自己破産開始決定前の滞納」を理由に供給が停止することはありません(開始決定後の滞納を理由に停止されることはあり得ます。)。
② 不法行為に基づく損害賠償請求権(二号・三号)
悪意(単なる故意を超える意図的な害意)が認められる不法行為によって他人に損害を与えた場合、その損害賠償請求権は非免責債権とされます(二号)。
また、故意または重大な過失によって人の生命・身体を害した場合の損害賠償請求権も、非免責債権とされます(三号)。
例えば、単なる不注意で交通事故を起こしてしまった場合はこれにあたりませんが、極度の酩酊状態で交通事故を起こし、被害者の生命身体に損害を負わせた場合は、重大な過失として非免責債権にあたる可能性があります。
③ 親族間・扶養義務に関する債務(四号)
民法上規定される夫婦の協力義務、扶助義務、婚姻費用・養育費・子の監護義務、扶養義務などに基づく金銭債務は非免責債権とされます。
たとえば、養育費や婚姻費用の分担義務は、非免責債権として、免責決定後も支払い義務が残ります。
養育費や婚姻費用についてはこちらの記事をご覧ください。
④ 雇用関係債権(五号)
破産者が使用者であった場合、従業員に対する未払賃金債権、預り金返還債権などは非免責債権となります。
ただし、破産者が法人の場合、根本的に支払い義務は消滅します。
法人は破産手続によって存在そのものが消滅するからです。
⑤ 罰金・過料など(七号)
罰金、科料といった刑事罰や、過料といった行政罰に基づく支払い義務も非免責債権に該当します。
交通違反の反則金や刑罰として課せられた罰金・科料は、免責によっても支払い義務を免れることはできません。
なお、刑事罰として罰金が課され、それが支払えない場合、最終的には労役場に留置され、強制的な作業従事によって支払いに充てられることもあります。
3 免責不許可事由との違いは?
非免責債権と似た言葉で「免責不許可事由」というものがあります。
どちらも「免責がされない」という点では共通しますが、非免責債権は当該債権があったとしても、免責決定によって非免責債権以外の債権は免責されます。
これに対して、免責不許可事由がある場合、非免責債権がなくとも、そもそも原則として免責決定がされません。
ですので両者の違いはしっかりと押さえておきましょう。
免責不許可事由についてはこちらの記事をご覧ください。
4 まとめ
自己破産をすればすべての借金が帳消しになる――
そのように誤解されがちですが、実際には非免責債権に該当する債務は、破産後も支払い義務が残ります。
税金や養育費、罰金、悪意の不法行為による損害賠償債権などは、たとえ免責許可が下りても「消えない債務」です。
「どこまでが免責されるのか」「破産しても支払わなければならない債務は何か」――
その疑問を明確にすることが、再出発への第一歩です。
破産を検討されている方は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
あかがね法律事務所では破産事件も多く取り扱っています。
以下よりご相談お待ちしております。