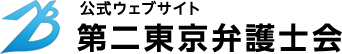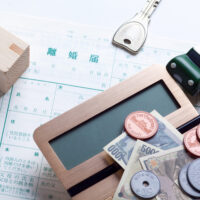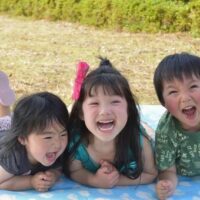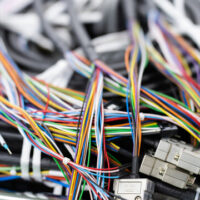面会交流とは? ~親権者でない親と子どもの交流権

わが子と面会交流をしたいのに、相手方がこれを許してくれない・・・・
今回はそんな悩みに関して、そもそも面会交流とは何かについて解説します。
1 面会交流の意義と法的根拠
面会交流とは、離婚後または別居中に、子どもを監護していない親(非監護親)が子どもと会ったり連絡を取ったりする「親子交流」のことを指します。
民法第766条は、離婚の際、面会交流の方法を決めることを定め、子どもの利益を考慮すべき旨規定しています。
| (離婚後の子の監護に関する事項の定め等) 第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。 |
ただし、面会交流は「権利」であると同時にその制約もあり得ます。つまり、非監護親の交流を求める権利が保障される一方、交流が子どもの福祉に反すると判断される場合には制限が認められます。
2 面会交流の期間と対象年齢
面会交流は、原則として子どもが成人(法律上は18歳)になるまで取り決めておくことができます。
ただし、子どもが年齢を重ねると本人の意思も尊重されるようになるため、必ずしも「成人まで面会交流を保証する」ものとはならないことに注意が必要です。
3 面会交流の取り決め方・実施方法
⑴ 話し合い・協議で決めることが望ましい
面会交流の方式や頻度、時間・場所、連絡方法、宿泊の有無などは、まず親同士の話し合いで決めることが基本です。
離婚時に面会交流を取り決めておけば、離婚後に面会交流を理由に争う可能性が減ります。
なお、合意できた内容は、離婚協議書、公正証書などに書面化しておくと、後日のトラブル防止につながります。
⑵ 調停・審判による決定(裁判所手続)
話し合いで決まらない場合、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることができます。これを「子の監護に関する処分(面会交流)調停」といいます。
調停で合意できなければ、審判へと移行し、裁判官が面会交流の可否・方法を決定します。
⑶ 調停での実務的手順・注意点
調停では、申立ての理由・経緯、双方の主張、子どもとの過去の交流状況、面会方式・条件案、不安点などが問われます。
試行的面会交流が行われる可能性もあります。試行的面会交流とは、家庭裁判所調査官立会いのもと、家庭裁判所庁舎内の児童室などで短時間交流を試みる方式で、その状況を踏まえて調停を進めることをいいます。
⑷ 面会交流が認められない・制限されるケース
面会交流は、子どもの安全・健全な成長を妨げる恐れがある場合には制限される可能性があります。
例えば、DV・虐待の可能性や子どもが心理的に不安定である場合がこれに該当します。
また、一度決まった面会交流の約束を守らない(正当な理由なく面会交流をさせない)監護親に対しては、「間接強制」という形で、交流をさせなかった行為1回あたりの制裁金を定める方法によって面会交流を強制させることができます。ただし、面会そのものを強制的に実施させる「直接強制」は認められていません。
4 まとめ
面会交流は、子どもの健やかな成長にとって重要な権利である一方、離婚後の親同士の感情や生活状況によって、実施方法をめぐるトラブルが起こりやすい問題でもあります。
「相手が約束を守らない」「子どもが会いたがらない」「再婚後にトラブルが起きた」など、状況によっては家庭裁判所への申立てや調停対応が必要になるケースも少なくありません。
こうした複雑なケースでは、弁護士に早めに相談することが大切です。弁護士が間に入ることで、相手との交渉や家庭裁判所での手続きをスムーズに進め、子どもとあなたにとって最善の解決を目指すことができます。
面会交流に関する不安や疑問がある方は、まずは一度、弁護士にご相談ください。あなたとお子さんの新しい生活を、法的な側面からしっかりとサポートいたします。
あかがね法律事務所では、離婚事案も多数取り扱っています。
以下よりお気軽にご相談ください。