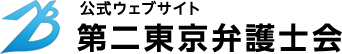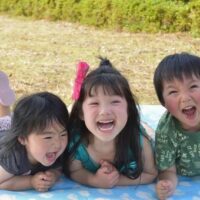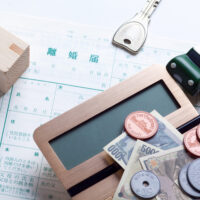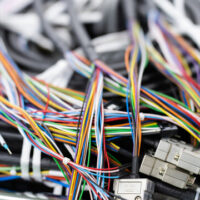養育費とは何か? ~子どものための義務と制度

離婚を考えているけど、離婚後の養育費が心配・・・
このように悩まれている方が多いのではないでしょうか?
今回は、養育費について請求できる時期や対象について解説します。
1 養育費って?
養育費とは、親が子どもの生活を維持・教育を行ううえで必要な費用を負担する制度です。法的には、扶養義務ではなく、親と同水準の生活を保障する「生活保持義務」と考えられています。
法務省も養育費について、「子どもの最低限の生活を支える義務」であり、子どもが自立するまでの間、衣食住・教育・医療などに必要な費用を含むと定義しています。
民法第766条1項で、子どもを監護し養育する親は、他方の親に対して養育費を請求できる旨が定められています。 これが養育費請求の根拠となります。
| (離婚後の子の監護に関する事項の定め等) 第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。 |
2 いつ請求できる?
離婚を検討しているのであれば、離婚後に備えていつでも請求可能です。
ただし、実際の支払義務が発生するのは原則として離婚後からになります。
子の生活に関する重要な事項ですので、早めに請求をしておきましょう。
3 請求の流れと手続きの実務ポイント
① まずは協議・交渉
婚姻費用と同様に、請求をする際、まずは配偶者と話し合い、支払金額・支払期日・支払方法などをできるだけ具体的に決めておくと、後のトラブルを防ぎやすくなります。
もし支払いに関する合意ができたら、養育費に関する合意書を作成しておくとよいです。
将来不払いになったときに備えて、強制執行認諾条項を入れた公正証書形式で作成することも検討すべきです。
② 調停の申し立て
協議で合意できない場合、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てます。調停手続では、調停委員が双方の事情を聴きながら調整・助言を行います。
調停が不成立の場合、審判手続(裁判官による強制的な決定)へ移行します。
調停や審判の結果、支払いがなされることになった場合、裁判所が作成する調停調書や審判書には強制執行の力が付与されます。
したがって、今後、相手が支払わない場合には、給料や預貯金の差押えなど強制執行をすることも可能です。
③ 必要資料・証拠の準備
調停・審判で有利な主張をするためには、以下のような資料を準備しておくことが重要です。
- 自分の収入・所得を証明する資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書など)
- 義務者側の収入状況を把握できる資料(できれば源泉徴収票等)
- 現在の生活費・支出明細(家賃、光熱費、医療費、保険料、通信費など)
- 子どもの教育費・医療費、保育料などの費用記録
- クレジットカード明細・領収書など日常的な支出記録
こうした証拠を整えておけば、「このくらいの金額が必要だ」という主張を支える根拠になります。
④ 計算方法(養育費算定表)
裁判所では、「養育費算定表」という基準表を公開しています。基本的にはこちらの算定表を参考にして、請求可能金額の目安が定められています。算定表は、夫婦の年収や子ども人数・年齢などから養育費を導いています。
ただし、算定表の数値はあくまで基準であり、個別事情(支出規模、特別事情など)を考慮して調整されることがあります。
詳しくはこちらをご参照ください。
【養育費算定表】
4 支払期間
支払期間としては、特に決まりがなければ原則、「子どもが18歳になる誕生月まで」とされます。これは18歳が成人年齢となっているからです。
ですが、「子どもが20歳になる誕生月まで」と合意することも多いです。あくまでも養育費は、成人年齢に達したかどうかではなく、「子どもが社会的・経済的に自立ができているかどうか」で判断され、支払われるべきものだからです。
もちろん、「大学卒業まで養育費を支払う」という条項内容も可能です。
ただし、離婚後すでに相当期間が経過している場合、毎月の養育費請求権は5年で時効によって消滅してしまうため注意が必要です。
5 よくある質問・注意点
Q1:婚姻費用と養育費はどう違うの?
→ 婚姻費用は、夫婦が婚姻関係にある間の生活費全体(子どもの養育費含む)を指します。
一方、養育費は離婚後、親権を持たない側が子どもの生活・教育費を支払う義務を指します。一般的には、婚姻費用の方が広い範囲を含むため、額も大きくなることがあります。
Q2:請求できる金額は2分の1が基準?
→ 財産分与のように単純な「半分ルール」はありません。算定表および個別事情をもとに算定されるため、義務者と権利者の収入比率、支出状況、子どもの年齢・人数などを総合的に判断します。
財産分与についてはこちらの記事をご覧ください。
Q3:将来収入が変わったら?
→ 将来収入が変わった場合、養育費の増額・減額請求も可能です。
Q4:請求してから支払われるまでどのくらいかかる?
→ 調停申立て後は、調停が成立すれば比較的早期に支払いが開始します。しかし、調停が長引くような、争点が多いケースでは数か月以上かかることもあり得ます。
Q5:自分で手続きできる?
→ 個人でも調停申立ては可能ですが、相手方との交渉や証拠精査、書面作成などの法的手続きには専門知識が必要です。特に複雑な事情が絡む場合は、弁護士に依頼した方が安心です。
6 まとめ
養育費は、子どもの健全な生活と将来を守るために欠かせない制度です。しかし、実際には「相手が支払ってくれない」「金額に納得できない」「算定表のどの金額が妥当なのかわからない」といったトラブルが少なくありません。
さらに、調停や審判といった手続を経る場合には、証拠の整理等の準備が必要であり、専門的な知識が求められます。
弁護士に依頼すれば、適正な養育費額の算定や調停での主張等手厚くサポートできます。何よりも、あなたやお子さまの生活の安定を第一に考えた解決策を一緒に見つけることができます。
養育費のことでお悩みの方は、一人で抱え込まず、ぜひ弁護士にご相談ください。早めの行動が、将来の安心につながります。
あかがね法律事務所では、離婚事案も多数取り扱っています。
以下よりお気軽にご相談ください。