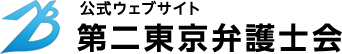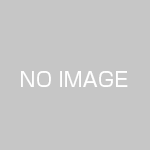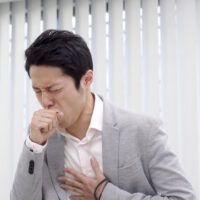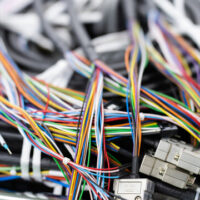アスベスト(石綿)で肺がんになった場合の救済給付の内容は?
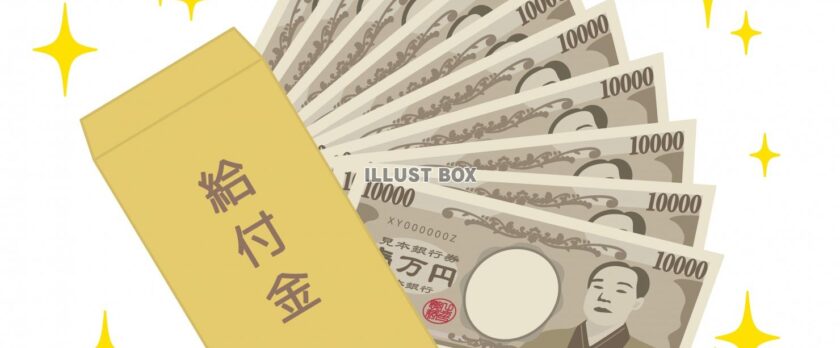
前回記事では、アスベストで肺がんになった場合に救済給付を受けられるか説明しました。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
さて、石綿健康被害救済法による救済給付は、患者様の状況等によって給付の内容や請求期限が異なります。
そこで、今回は、患者様の状況ごとにどのような給付が受けられるのか等を紹介します。
1 患者様が療養中の場合
患者様が療養中で、患者様ご本人が申請する場合に受け取ることができる給付は医療費と療養手当の2種類です。
⑴ 医療費
まず、医療費は、肺がんの療養を開始した日(申請の3年以上前から療養している場合には、申請日の3年前の日)以降に必要となった医療費のうち自己負担した分が支給されます。
また、医療費については、原則として支払日の翌日から2年以内に請求する必要があります。ただし、療養を開始した日から申請日の前日までの医療費については、例外的に、申請日から2年以内に請求すれば良いものとされています。
なお、石綿を吸入することにより肺がんになったという認定を受けた後には、石綿健康被害手帳が交付され、交付後は、同手帳を保険医療機関に提示することで窓口での自己負担の支払いは免除されます。
⑵ 療養手当
療養手当は、基準日の属する月の翌月から、支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給されることとなっています。金額は10万3870円で、原則として、偶数月に、前月及び前々月分が支給されます。療養手当に関しては、請求期限は特に設けられていません。
2 患者様が肺がんで亡くなられた場合
患者様が肺がんで亡くなられた場合には、患者様のご遺族が救済給付を申請することができます。ただし、ご遺族であれば誰でも請求することができるというわけではなく、患者様が亡くなられた当時、患者様と生計を同じくしていたご親族のうち、下記の優先順位が最も高い方が請求できるとされています。
優先順位は、①(事実婚を含む)配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹です。
また、患者様が亡くなられた時期によって請求期限が異なるため、この点にも注意が必要です。
患者様が平成18年3月6日以前に亡くなられた場合は、令和4年3月27日まで、平成18年3月27日~平成20年11月30日に亡くなられた場合は、令和5年12月1日まで、平成20年12月1日以降に亡くなられた場合は、死亡した日の翌日から15年が請求期限とされています。
なお、亡くなられた時期に関わらず、特別遺族弔慰金280万円、特別葬祭料19万9000円の救済給付を受け取ることができます。
3 患者様が療養中に申請して認定を受け、その後亡くなられた場合
患者様が療養中に申請して認定を受け、その後亡くなられた場合に受け取ることのできる救済給付は葬祭料、未支給の医療費・療養手当、救済給付調整金の3つです。
⑴ 葬祭料
葬祭料は葬祭を行う方に支給されるもので、給付額は19万9000円です。葬祭料は、患者様が亡くなられた日の翌日から2年以内に請求する必要があります。
⑵ 未支給の医療費・療養手当
未支給の医療費・療養手当は請求権を有するご遺族※に支給されます。医療費の自己負担分については、請求できる日から2年以内に請求する必要がありますが、療養手当については、別途請求する必要はありません。
⑶ 救済給付調整金
救済給付調整金は、患者様本人又はご遺族に支給された医療費・療養手当の合計金額が280万円に満たない場合に差額分が請求権を有するご遺族※に支給されるというものです。救済給付調整金は、患者様が亡くなられた日の翌日から2年以内に請求する必要があります。
※患者様と生計を同じくしていたご親族のうち、下記の優先順位が最も高い方が請求できるとされています。
優先順位は、①(事実婚を含む)配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹です。
4 給付申請に必要な書類
石綿健康被害救済法に基づく給付を受けるためには、必要な資料を申請窓口へ提出する必要があります。亡くなられた患者様について救済給付を申請する場合には、亡くなられた時期によって必要書類が異なるため、特に注意が必要です。以下で、申請の際にどのような書類が必要となるのかをご説明します。
なお、いずれの場合も申請窓口は環境再生保全機構、各地の保健所または環境省の地方環境事務所です。
①療養中の患者様ご本人が申請する場合
療養中の患者様ご本人が救済給付の申請を行う場合、申請書類として、認定申請書、戸籍の記載事項を確認できる書類(戸籍謄本、住民票等)、療養手当請求書、医学的資料として、肺がん診断書、エックス線検査・CT検査などの画像、病理診断書等の根拠資料が必要です。医学的資料は病院に準備をお願いしていただく必要がございますのでご注意ください。
②患者様が亡くなられた後にご遺族が申請する場合
亡くなられた患者様について救済給付を申請する場合には、亡くなられた時期によって必要書類が異なります。
まず、平成18年3月27日以降に亡くなられた患者様で、認定の申請を行っていなかった方についてご遺族が申請する場合、申請書類として、特別遺族弔慰金等請求書、身分関係を証明できる戸籍類(戸籍謄本、改製原戸籍等)、生計を同じくしていたことを証明できる書類(戸籍の附票や保険証の写し等)、死亡診断書または死体検案書の写し、医学的資料として、肺がん診断書、エックス線検査・CT検査などの画像、病理診断書等の根拠資料が必要です。
医学的資料は病院に準備をお願いしていただく必要がございますのでご注意ください。
平成18年3月26日以前に亡くなられた患者様についてご遺族が申請する場合、申請書類として、特別遺族弔慰金等請求書、身分関係を証明できる戸籍類(戸籍謄本、改製原戸籍等)、生計を同じくしていたことを証明できる書類(戸籍の附票や保険証の写し等)、死亡診断書等を法務局に照会することに関する同意書、医学的資料として石綿が原因であることの根拠に関する報告書、石綿が原因であると判断した根拠となる胸部エックス線・CT検査の画像等が必要です。
医学的資料は病院に準備をお願いしていただく必要がございますのでご注意ください。
5 建設アスベスト給付金も申請する場合
石綿健康被害救済法に基づく給付を受ける場合、各種の検査方法によって、石綿にばく露したことで肺がんに罹患したと判定されることが重要です。
そのため、申請に際して、アスベストばく露作業の具体的内容等の情報は必ずしも必要とされていません。
一方、建設アスベスト給付金の場合、一定の建設業務に携わっていたことが条件となっています。そのため、建設アスベスト給付金の申請をお考えの場合は、アスベストのばく露歴に関する情報を改めて確認する必要があるのでお気を付けください。
6 まとめ
いかがでしたでしょうか?
補償のための申請には法的判断が必要になります。
アスベスト(石綿)による肺がんかもしれないと思った際には、一度、法律事務所に相談をしましょう。
あかがね法律事務所はアスベストに関する補償給付申請等も取り扱っております。
下記よりご相談をお待ちしております。